「あっちのトラックのあの帯域をトリガーにして、こっちのトラックのこの帯域を下げたい」の実装方法について書いておきます。
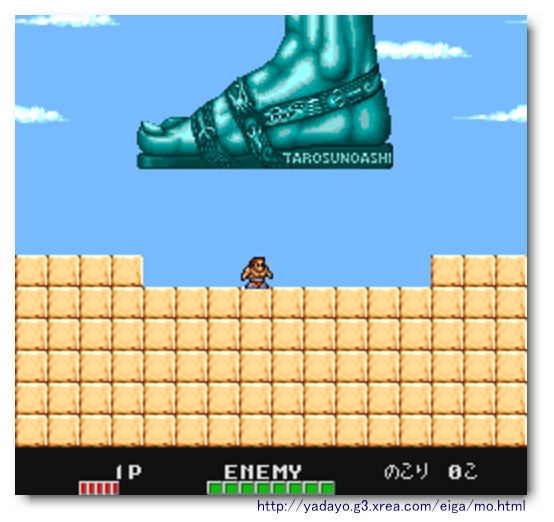
(2020年5月22日更新)
■実装方法
まずはSCで下げたいトラックで、ダイナミックEQのSCをオン。

トリガーにしたいドラム全体のトラックで、センド先を1つ作ります。

センド先を表示。
センドトリガーは音を出しません。
出力先を「No Bus」にします。

てきとーにハイカットする。

右下。センドを接続。ベースのSC用EQを指定。
センドレベルは最大にしておくと後で確認作業がやりやすい。
SC元のダイナミックEQを表示。

センドトリガーのレベルと、ダイナミックEQを両方見ながら調節。
・応用
必要に応じて、いくつかのセンドトリガーを仕込むこともできます。
これにより特殊なプラグインを使わなくても「あの楽器のあの帯域をトリガーにしたい」という夢がかないます。
・カットEQあれこれ
なお、こういう非音楽的な加工をする時には、異常なシェイプ角度を持つEQが役立ちます。
変な加工ならまかせとけ。Toneboosters FLX。

古き良き変態。一刀両断のSpline EQ。今でもたまに使う。

画面の縮尺が違ってすみません。
でもSPANの表示でより垂直に切れていることは一目瞭然ですね。
なお、SCのトリガーのためにピークを抽出できれば良いだけなので、付属EQで全く問題ありません。
なお、EQ自体の画面内で垂直に見えることと、実際にどう音が加工されたかはあまり関係ありません。GUIに騙されないようにしましょう。
■関連記事(外部サイト)
Quadroバスを使うSC実装方法について詳しく解説されています。
そもそもSCはDAWの機能として内蔵されるまではこういう方法などを使ってド根性で実装されていましたよ、ということでご先祖様に感謝しましょう。
そもそもDAWの、デジタル環境の最大のメリットは自由なルーチングです。それを使わずに、新しいプラグインの機能にばかり頼っていてはいけません。
もう一発。SC基礎。複数の方法によるSC実装手順。
基本的すぎることをちゃんと説明する人は偉いと思う。